服部英雄のホームページ
『蒙古襲来』新聞書評
2015.3.15 08:40
産経ニュース(産経新聞)から
上級専門委員・気仙英郎が読む『蒙古襲来』(服部英雄著)
神風」は吹かなかった!?
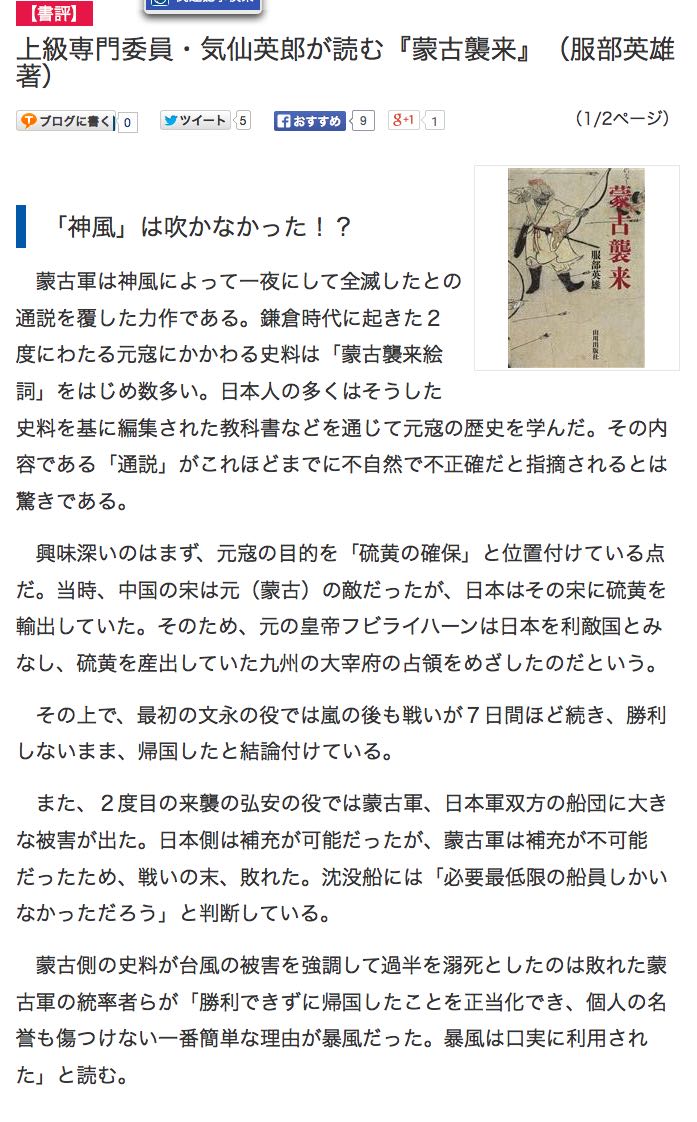 蒙古軍は神風によって一夜にして全滅したと の通説を覆した力作である。
鎌倉時代に起きた2度にわたる元寇にかかわる史料は「蒙古襲来絵詞」をはじめ数多い。
日本人の多くはそうした史料を基に編集された教科書などを通じて元寇の歴史を学んだ。
その内容である「通説」がこれほどまでに不自然で不正確だと指摘されるとは驚きである。
興味深いのはまず、元寇の目的を「硫黄の確保」と位置付けている点だ。
当時、中国の宋は元(蒙古)の敵だったが、日本はその宋に硫黄を輸出していた。
そのため、元の皇帝フビライハーンは日本を利敵国とみなし、硫黄を産出していた
九州の大宰府の占領をめざしたのだという。
その上で、最初の文永の役では嵐の後も戦いが7日間ほど続き、勝利しないまま、帰国したと結論付けている。
また、2度目の来襲の弘安の役では蒙古軍、日本軍双方の船団に大きな被害が出た。
日本側は補充が可能だったが、蒙古軍は補充が不可能だったため、戦いの末、敗れた。
沈没船には「必要最低限の船員しかいなかっただろう」と判断している。
蒙古側の史料が台風の被害を強調して過半を溺死としたのは敗れた蒙古軍の統率者らが
「勝利できずに帰国したことを正当化でき、個人の名誉も傷つけない一番簡単な理由が暴風だった。
暴風は口実に利用された」と読む。
こうした史料の読み間違いを見直してみえてきたものは何か。
神風を政治的に利用した人々の存在である。
神風の政治的利用は近代にいたるまで続き、太平洋戦争の「神風特攻隊」という悲劇につながった。
著者によれば、歴史学研究には推理が不可欠だが、合理的で科学的な解釈に基づく仮説が必要で、
問われるのは妥当性、客観性、再現性だという。本作はそのスタンスに違うことなく史料を徹底的に再読することに徹している。
著者は「権威主義、および際限なき孫引きに守られてきた通説こそは、砂上の楼閣だった」と断言しているが、
今後、他の歴史学者らとの活発な論争が期待される。(山川出版社・2400円+税)
評・気仙英郎(上級専門委員)
蒙古軍は神風によって一夜にして全滅したと の通説を覆した力作である。
鎌倉時代に起きた2度にわたる元寇にかかわる史料は「蒙古襲来絵詞」をはじめ数多い。
日本人の多くはそうした史料を基に編集された教科書などを通じて元寇の歴史を学んだ。
その内容である「通説」がこれほどまでに不自然で不正確だと指摘されるとは驚きである。
興味深いのはまず、元寇の目的を「硫黄の確保」と位置付けている点だ。
当時、中国の宋は元(蒙古)の敵だったが、日本はその宋に硫黄を輸出していた。
そのため、元の皇帝フビライハーンは日本を利敵国とみなし、硫黄を産出していた
九州の大宰府の占領をめざしたのだという。
その上で、最初の文永の役では嵐の後も戦いが7日間ほど続き、勝利しないまま、帰国したと結論付けている。
また、2度目の来襲の弘安の役では蒙古軍、日本軍双方の船団に大きな被害が出た。
日本側は補充が可能だったが、蒙古軍は補充が不可能だったため、戦いの末、敗れた。
沈没船には「必要最低限の船員しかいなかっただろう」と判断している。
蒙古側の史料が台風の被害を強調して過半を溺死としたのは敗れた蒙古軍の統率者らが
「勝利できずに帰国したことを正当化でき、個人の名誉も傷つけない一番簡単な理由が暴風だった。
暴風は口実に利用された」と読む。
こうした史料の読み間違いを見直してみえてきたものは何か。
神風を政治的に利用した人々の存在である。
神風の政治的利用は近代にいたるまで続き、太平洋戦争の「神風特攻隊」という悲劇につながった。
著者によれば、歴史学研究には推理が不可欠だが、合理的で科学的な解釈に基づく仮説が必要で、
問われるのは妥当性、客観性、再現性だという。本作はそのスタンスに違うことなく史料を徹底的に再読することに徹している。
著者は「権威主義、および際限なき孫引きに守られてきた通説こそは、砂上の楼閣だった」と断言しているが、
今後、他の歴史学者らとの活発な論争が期待される。(山川出版社・2400円+税)
評・気仙英郎(上級専門委員)
目次へ戻る
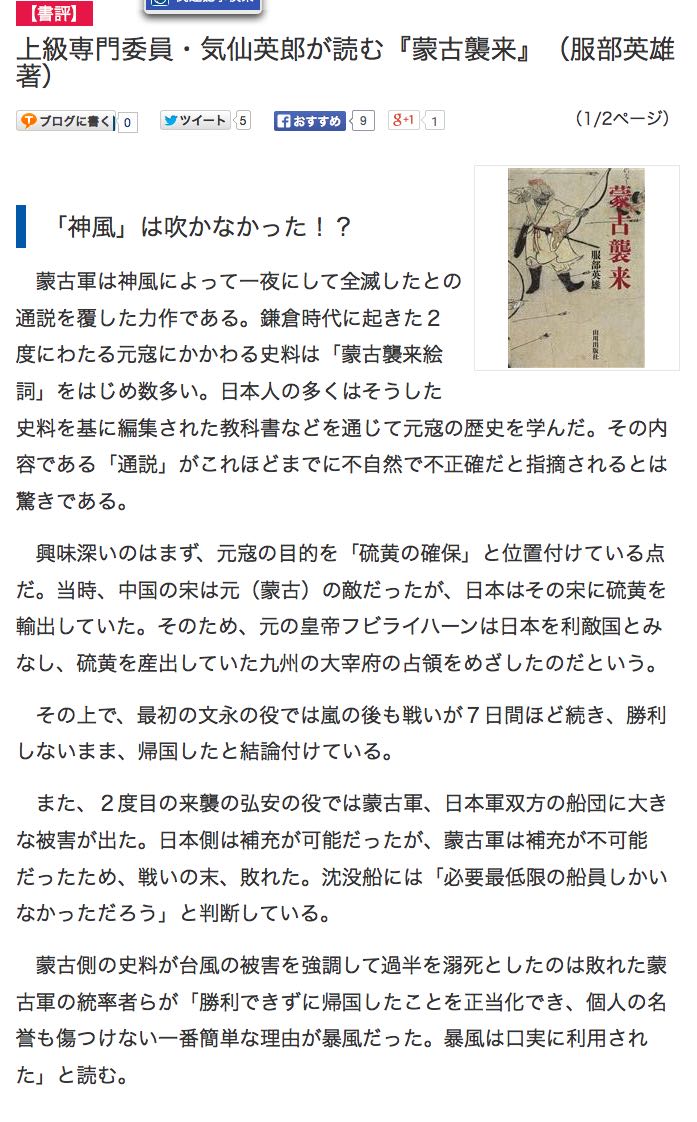 蒙古軍は神風によって一夜にして全滅したと の通説を覆した力作である。
鎌倉時代に起きた2度にわたる元寇にかかわる史料は「蒙古襲来絵詞」をはじめ数多い。
日本人の多くはそうした史料を基に編集された教科書などを通じて元寇の歴史を学んだ。
その内容である「通説」がこれほどまでに不自然で不正確だと指摘されるとは驚きである。
興味深いのはまず、元寇の目的を「硫黄の確保」と位置付けている点だ。
当時、中国の宋は元(蒙古)の敵だったが、日本はその宋に硫黄を輸出していた。
そのため、元の皇帝フビライハーンは日本を利敵国とみなし、硫黄を産出していた
九州の大宰府の占領をめざしたのだという。
その上で、最初の文永の役では嵐の後も戦いが7日間ほど続き、勝利しないまま、帰国したと結論付けている。
また、2度目の来襲の弘安の役では蒙古軍、日本軍双方の船団に大きな被害が出た。
日本側は補充が可能だったが、蒙古軍は補充が不可能だったため、戦いの末、敗れた。
沈没船には「必要最低限の船員しかいなかっただろう」と判断している。
蒙古側の史料が台風の被害を強調して過半を溺死としたのは敗れた蒙古軍の統率者らが
「勝利できずに帰国したことを正当化でき、個人の名誉も傷つけない一番簡単な理由が暴風だった。
暴風は口実に利用された」と読む。
こうした史料の読み間違いを見直してみえてきたものは何か。
神風を政治的に利用した人々の存在である。
神風の政治的利用は近代にいたるまで続き、太平洋戦争の「神風特攻隊」という悲劇につながった。
著者によれば、歴史学研究には推理が不可欠だが、合理的で科学的な解釈に基づく仮説が必要で、
問われるのは妥当性、客観性、再現性だという。本作はそのスタンスに違うことなく史料を徹底的に再読することに徹している。
著者は「権威主義、および際限なき孫引きに守られてきた通説こそは、砂上の楼閣だった」と断言しているが、
今後、他の歴史学者らとの活発な論争が期待される。(山川出版社・2400円+税)
評・気仙英郎(上級専門委員)
蒙古軍は神風によって一夜にして全滅したと の通説を覆した力作である。
鎌倉時代に起きた2度にわたる元寇にかかわる史料は「蒙古襲来絵詞」をはじめ数多い。
日本人の多くはそうした史料を基に編集された教科書などを通じて元寇の歴史を学んだ。
その内容である「通説」がこれほどまでに不自然で不正確だと指摘されるとは驚きである。
興味深いのはまず、元寇の目的を「硫黄の確保」と位置付けている点だ。
当時、中国の宋は元(蒙古)の敵だったが、日本はその宋に硫黄を輸出していた。
そのため、元の皇帝フビライハーンは日本を利敵国とみなし、硫黄を産出していた
九州の大宰府の占領をめざしたのだという。
その上で、最初の文永の役では嵐の後も戦いが7日間ほど続き、勝利しないまま、帰国したと結論付けている。
また、2度目の来襲の弘安の役では蒙古軍、日本軍双方の船団に大きな被害が出た。
日本側は補充が可能だったが、蒙古軍は補充が不可能だったため、戦いの末、敗れた。
沈没船には「必要最低限の船員しかいなかっただろう」と判断している。
蒙古側の史料が台風の被害を強調して過半を溺死としたのは敗れた蒙古軍の統率者らが
「勝利できずに帰国したことを正当化でき、個人の名誉も傷つけない一番簡単な理由が暴風だった。
暴風は口実に利用された」と読む。
こうした史料の読み間違いを見直してみえてきたものは何か。
神風を政治的に利用した人々の存在である。
神風の政治的利用は近代にいたるまで続き、太平洋戦争の「神風特攻隊」という悲劇につながった。
著者によれば、歴史学研究には推理が不可欠だが、合理的で科学的な解釈に基づく仮説が必要で、
問われるのは妥当性、客観性、再現性だという。本作はそのスタンスに違うことなく史料を徹底的に再読することに徹している。
著者は「権威主義、および際限なき孫引きに守られてきた通説こそは、砂上の楼閣だった」と断言しているが、
今後、他の歴史学者らとの活発な論争が期待される。(山川出版社・2400円+税)
評・気仙英郎(上級専門委員)