服部英雄のホームページ
無断転載はお断りします。引用の場合は出典を明記ください。この頁の製作は06/10/1206.10.01七隈史学会での報告「蒙古襲来の新研究」の概要と、質疑応答、および追加
発表要旨
主戦場であった鳥飼干潟の地理的歴史的な位置を明らかにしつつ、日本を侵攻する外国軍の作 戦行動を刀伊の入寇と比較した。警固所から大宰府を攻撃するパターンを読み取りうる。文永の 役では、警固所のある赤坂で10月20日に合戦があった。つづいて10月24日に太宰府の攻防 戦があった。そのことについては『関東年代記』が記している。従来、研究者がこの記事を無視し、 捨ててきたのは、翌朝元軍が戻って博多湾に船がいなかったとする『八幡愚童訓』の強い影響であ る。しかし白衣の神が戦って、翌日元軍が姿を消したという『八幡愚童訓』のストーリーは荒唐無 稽である。リアルタイム史料である『勘注記』『吉続記』によって情報伝達の日から逆算して正し い合戦を復原できる(この点は「文永十一年冬の嵐」『歴史を読み解く』に記述ずみ、今回『吉続 記』記主で蔵人であった吉田経長と、10年後にやっと蔵人になる『勘注記』記主・広橋兼仲とへ の情報伝達の差にふれた・スライド)。
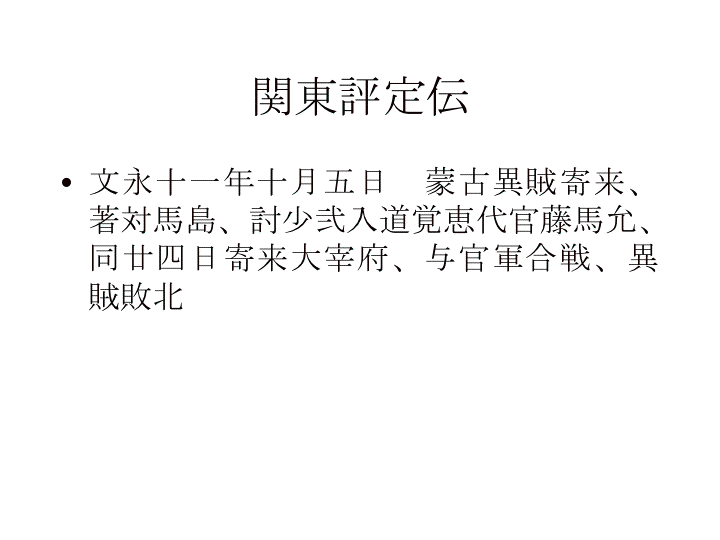
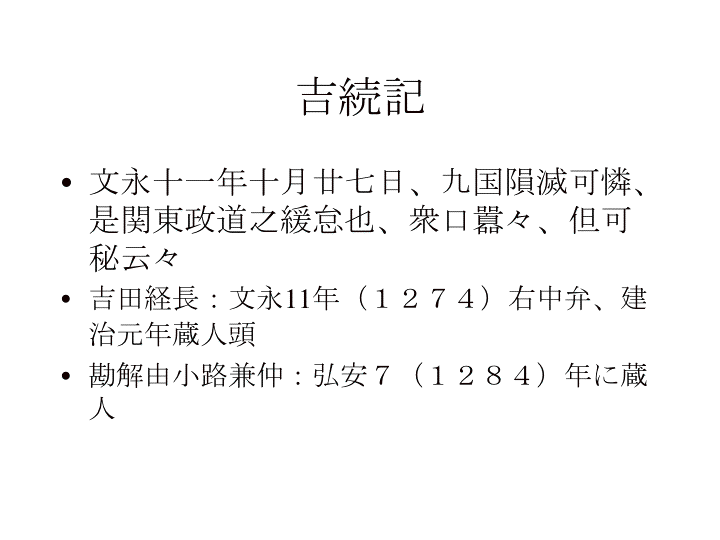
つづいて蒙古襲来絵詞(竹崎季長絵詞)の検討を行った。これは『日本歴史』698に発表した 見解を踏襲したものだが、奥書A(泰盛の御こと、後巻42紙)について、その記述内容と本文の記述 との矛盾を新たに指摘した。奥書Aでは季長が鎌倉幕府から特別な厚遇を受けたように書いている。 太宰府経由で恩賞を受けた百二十人との差異を強調し、直接に馬をもらったと書いている。 あたかも幕府の馬をもらったかのような記述だが、本文によればかれは泰盛個人(厩別当 左枝五郎)から私的に馬をもらったのである。太宰府経由で恩賞を受けた御家人たちは、 多くは安達泰盛との個人的関係はなかったので、馬をもらうはずはなかった。奥書Aの記 述は本文記述と合致せず、矛盾する。 奥書B(後巻43紙)では甲佐社の「桜の御威」のことが四度も登場し、くりかえし強調されるが、 建治元年、絵詞に見る活動期間中は桜の開花時期ではなかったから、唐突である。季長の行動からは 生まれにくい発想であり、別人(甲佐社関係者)の心象である。
宮次男氏(日本絵巻物全集)・表より引用
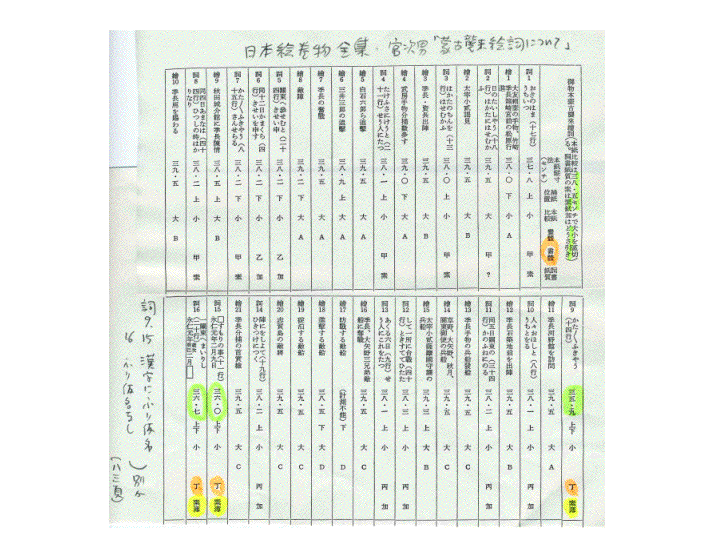
太田彩氏(日本の美術)・表より引用
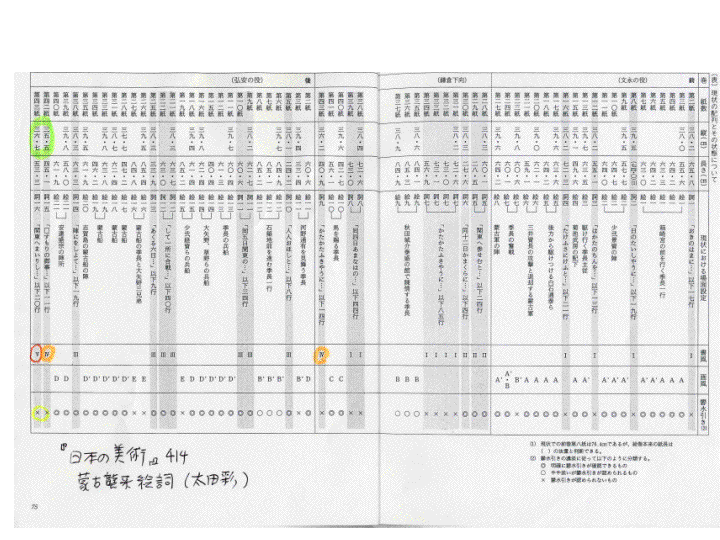
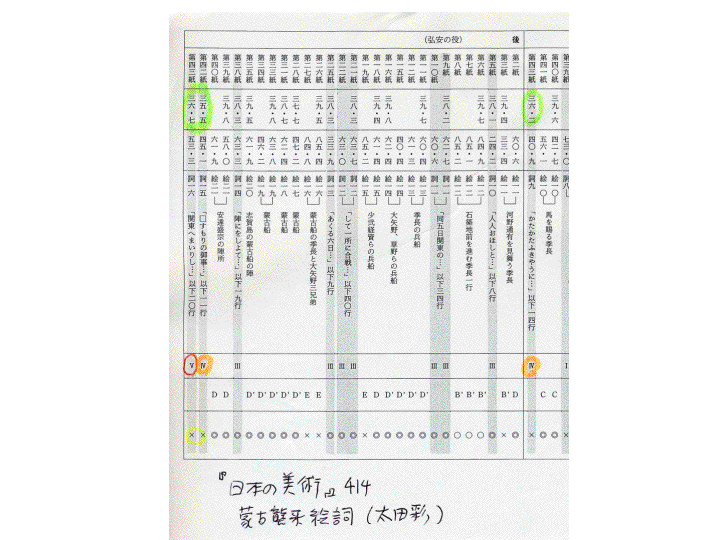
本文(かたがた)複製(右、前巻43紙)と奥書A(左、後巻42紙)の筆跡は一致
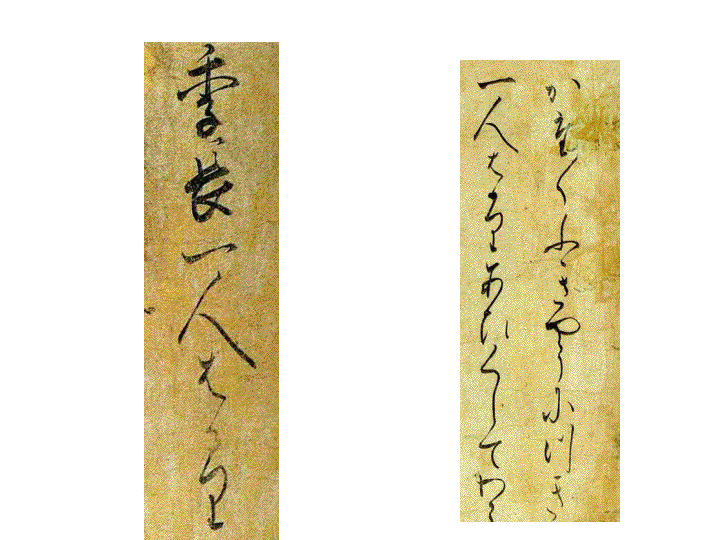
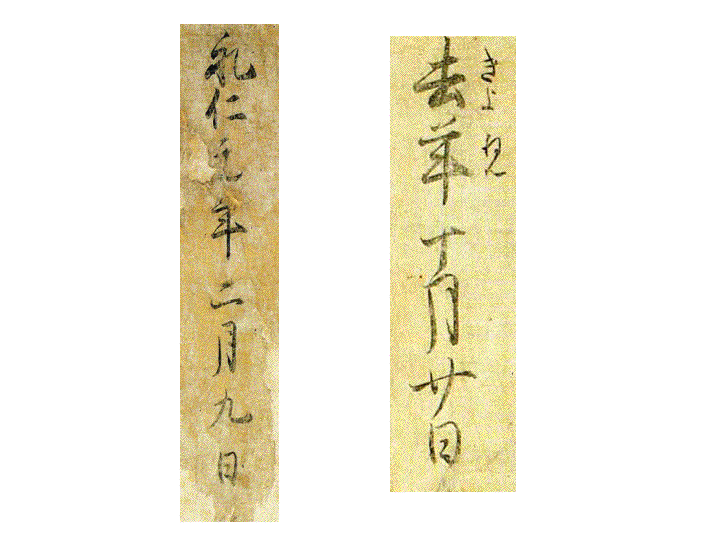
奥書Aと奥書B(後巻43紙)・似てはいるのだが。
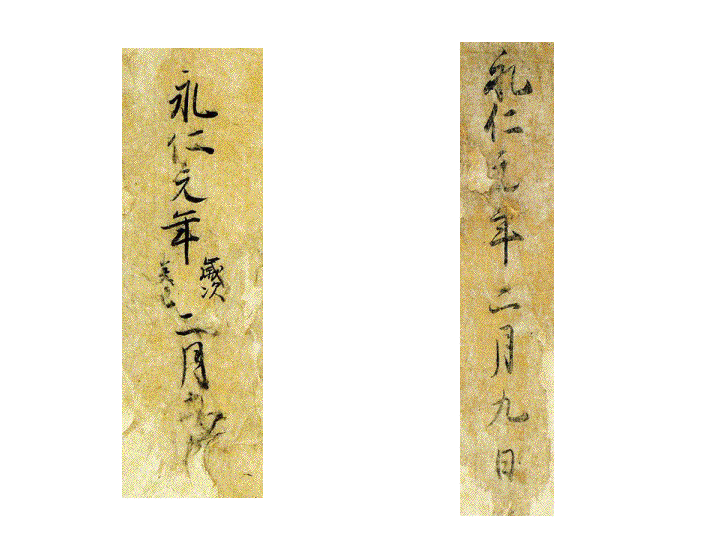
本文(かたがた)複製(右)と奥書B(左)の筆跡、印象は異なるが、似るところもある
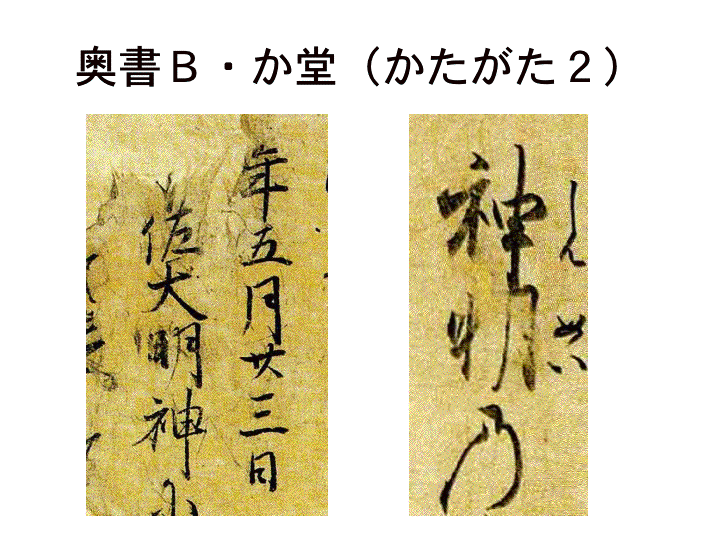
奥書Aと本文(かたがた)複製の筆跡が一致することについては、おそらく異議は、さしは さまれないだろう(スライド)。奥書A(後巻42紙)は本文(かたがた)複製(前巻43紙) と同時の成立であることも確実である。あるいは奥書Aのもとになる原本があったという 見解が提案されるかもしれない。しかし奥書Aは、本文の記述とはスタンス・コンテキス ト(文脈)を異にしている(上記した安達泰盛から個人的にもらった馬を、あたかも他の 御家人には与えられなかった恩典であるかのように記述した点など)。奥書Bの方は本文の 記述、つまり季長がほとんどケンカ別れをして、身内の見送りもなく、熊野先達・法眼き ょうしんのところにさえ、はなむけのわずらわしさから足を運ばなかったという記述と、 一致しない。 まったく別次元の発想から記述されている。関東・海東・東の桜とダジャレが続く。 本文とは整合性を持たないから、もととなる記述が季長自身によって残されていたとは考 えない。 奥書AとBの筆跡については、同筆と見る宮氏の説と、別筆とみる太田氏の見解がある。 部分的には相当に似ているが、決め手となるだけの筆跡の一致はない。 全体から受ける印象もちがう。同筆、別筆それぞれを想定して、奥書A、Bの成立を考える必要がある。 もし同筆ならば奥書Aも甲佐社関係者による作成である。 もし別筆ならば、模本(複製本)を作成した人物による後世の作成(創作)となる。奥書Aは誤 読によって要約したもので、本文と奥書は一体であると信じてきた過去の研究者も、この奥書の記 事から本文を読み込んで、そのため、誤解・誤認を生じることになった。しかしそれは安達泰盛を慕う竹 崎季長の心象の反映でもあった。季長は所領を獲得できた原点はあくまで、安達泰盛との接触に始 まったと考えていたのであり、その思いが絵詞詞書に投影された。そうした思いは、むろん虚偽で はないが、虚像を与えやすい記述になったのである。絵詞中、長門守護代子弟というエリート中の エリートで、季長の姉聟であった三井資長の旗印が全く描かれていないこと(旗印は季長の「三目 結い吉」のみ画かれている)、また「所領拝領の御下文」、「御分の御下文」、「庭中」といった文言は、 季長の思いの反映された文言でもあって、読む人間にとっては誤解しやすい記述となった。

上の絵に見える旗印が三目結い吉で季長の旗印である。下部は黒が退色して茶色になっている。 絵詞では、かれの一党にこの旗しか描かれない。だが三井の旗があったはずで、実態は異なっていただろう。
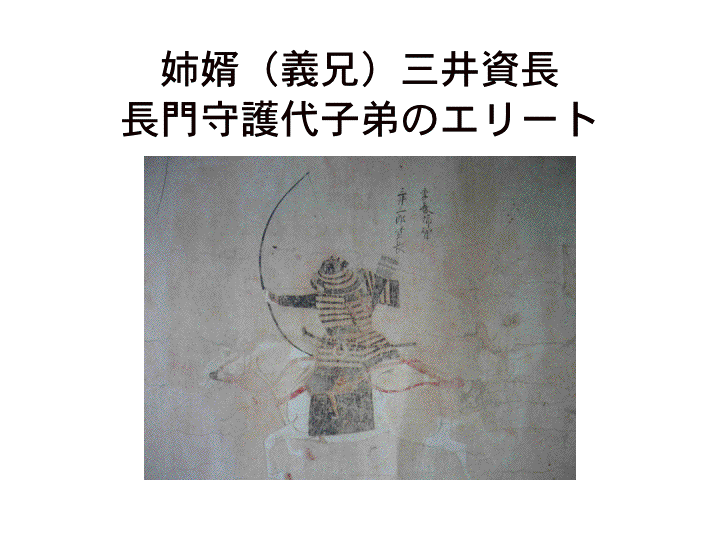

質疑
*以下、当日およびその後に、質疑をおよせいただいた方々への回答です。
Q 3人の蒙古兵が画かれた紙(23紙、24紙)は、左右でどうさ引きの有無が異なって おり、時期がちがうという太田彩氏の指摘がある。どう考えるか A 九州国博オープンのときに実物を見たが、そこまで注意してみなかった。太田氏は「23紙は 礬水引き(どうさ引き)がなく、24紙には礬水引きがある」としている。もし紙質が完全にちが うとすると、バラバラの時期にふたつの絵が画かれたことになるのだろうか。血を流してはねる馬 の上の季長(23紙)はこの絵詞(絵巻)には不可欠であり、力強く迫力もある。 24紙もなくてはならない。いずれかが時期を隔てた後世に画かれたとみることは、まった くあり得ないと思う。 なお太田氏は24紙には明確に礬水引きを確認できるとしているが、宮次男氏は前巻については 23紙にも24紙にも礬水引きを認めていない。なぜこのような見解のちがいが出るのだろうか。 よくはわからないし、われわれが現物を見ることはまずできないだろうが、検討すべき問題である。 Q 3人の蒙古兵の画風はむしろ後巻に似るという指摘があるが。 A 似たところはあるが、表情・筆致までも同じかどうかは自分では判断がつかない。一致する場 合でも一致しない場合でも、書き手は複数いたというのが私見である。 蒙古兵3人は制作過程の中で描かれたとする私見は成立する。 Q 奥書は本来あった長さを上下に切りつめているのではないか。これも太田氏の指摘があったと 記憶するが。本文にも縦の長さが短いものがあったのではないか。 A 奥書の長さは宮次男氏、太田彩氏で2ミリほどデータがちがう。破損があるため、はかり方が むずかしいのだろう。奥書A、Bとも天(上端)は水平部分、つまり旧状をとどめる箇所が多く残 っている。文字の上端までかなりの余白があり、切りつめたと考える根拠はない。地(下端)は水 平部分が残っていない。残存部分と行末の文字・改行前の高さで考えるほかないが、奥書A、Bと も十分に余裕を持たせて改行しており、切りつめたと考える必要はない。根拠もない。 本文長さは、詞書きでは38,2センチプラスマイナス1ミリないし2ミリである(第8紙のみ 39,5センチ)。本文絵は前巻では39センチプラス8ミリ、マイナス4ミリである。冒頭の第 3紙は38,0センチで短いが、冒頭だから破損を受けやすかったかもしれない。蒙古船を描いた 28紙は太田報告で37,7センチとされ、たしかに短いが、明らかに下部を失っていて、本来は 計測不可とすべきものである(宮次男氏は計測不能とする)。問題にしている43紙(「かたがた- --」複本)、そして奥書A、Bは36,2センチ、35,5センチ,36,7センチと、全体のな かにあって極端に縦が短い紙である。本文のなかには、こうした短い紙がない。そのことは諸氏が 一様に認めている(スライド参照)。 要するに紙質(長さ、素薄)、筆跡、内容が本文と質的にちがいすぎている。くわえて本文との 内容的な差異、矛盾がある。 別物と見なければならない。
Q 「庭中」にて申請された季長の恩賞は、他のものとは別に特別に即決された可能性がある。 A たしかに季長は「泰盛の御前にて庭中申事」としている。しかし彼はこの件に関しては訴人で はないし、裁許(判決)を受けたわけでもない。訴訟の当事者ではないから、「沙汰未練書」が規 定する庭中、『御成敗式目』にみえる庭中には、該当しない。『中世社会政治思想』では、「庭中」 の頭注で「訴訟手続きの過誤を救済するための再審制度であるが、この場合にはより広義に、直接 の上訴を指しているようである」と広く解釈している。また季長が訴え出た場所は安達泰盛私邸で あって、幕府の裁判所、問注所や引付の場ではなかった。 季長は10月3日に泰盛にその私邸にて会った。このときはたしかに面々が揃っているなかで面談 している(御内のしかるべき人々)。だが私邸内だから、安達泰盛家の重要メンバーであろ う。翌日4日も面会を求めにいったがあえず、以後11月1日まであえない。こういう状 況で、過誤審査としての庭中があったとはいえない。泰盛が「披露申し候」といっている ように、山内殿(北条時宗)が出席する場が、決定機関であろう。 したがって「庭中」ということばがあるからといって、幕府の機関審査を受けたという ことはできない。庭中は「陳情」「直訴」という意味のことばとして使われている。 Q 「上より御合戦の忠賞に、御領拝領の御下文」とあれば、上=将軍、御領拝領の御下文=恩賞 給付の将軍家政所下文、とすべきではないか。文永の役の恩賞が幕府より与えられたとみるべきで はないか。 A これは泰盛従者玉村のことばである。取り次ぎをした玉村がリップサービスでこうした発言を したことはあり得るが、結果として、そのあと泰盛が手渡した下文に「海東郷」の文言はなかった。 もし「海東郷」を得ていれば、かならずそのことにふれたはずである。ふつうならば下文 の引用があっても良いくらいである。また海東郷を得ていれば、その前提に見参を得てい たことは自明なのだから、くどくどと見参にこだわる発言はしないだろう。暫定的な内容 しかなかったから、「勧賞に預かりそうらはば---、その儀なく候はば-----」という発言に 続いたと考える。 Q 「申あげ候先の事、 君の見参にまかり入り候て、勧賞に預かり候はヽ、夜をもて日につぎ、...... その儀なく候はヽ、景資へ先の事御尋ねを被るべき旨申し上ぐべく候」という発言は、「申あげ候 先の事=過去に申しましたように」、という意味で解すべきではないか。だとすれば、文面は仮定 の形で良く、その後の文章は、過去に申請した結果として、自分だけが直接恩賞給付の下文が貰え、 120人は大宰府を経由して貰うことになったと言っているのでは。 A この段落は「やがて御下り候か」という泰盛の発言を受けてのもので、もし九州に下るといえ ば、先にいったような所領がなければ、幕府からの重要な指令を聞く場所もなく役に立てない、とい った自分の発言と矛盾する。そうならないようにと配慮した発言である。所領が与えられなかったから、 こうした発言になって、下文をもらう前と同じことばをくり返したと解釈するべきである。 「申しあぐべく候」というのは季長の主張であって、現在形・未来意志である。もしも過去 形なら「申しあげ候き」ではなかろうか。 古典文法に反した解釈はあやまりである。 Q 安達泰盛の御内人であったのなら、泰盛を顕彰するこのような絵巻を作成すること自体、 季長には危険すぎる行為ではなかったか。 A 泰盛の顕彰が危険ならば、絵詞自体成立し得ない。絵詞のなかで泰盛を顕彰しているこ とはまちがいのない事実である。政争に敗れた人物に対しても顕彰は可能であったといえる。 仮のたとえだが、源氏方となった平頼盛が兄清盛や甥の宗盛・知盛の法要や顕彰を行っ ても、とがめられることはなかったであろう。それを口実に危機に落ちることもなかった と考える。 Q 季長への厚遇、配慮がふつうではありえないといっているが、それだからこそ、絵詞を 作るきっかけになったのであろう。非常にまれなケースであったが、そうしたことは現実 にあったと見るべきではないか。 A 季長が鎌倉に上った成果は十分にあった。 第一に下文はかれが見参をうる資格を持つ人物だということを担保した。第二が泰盛との 結びつきである(御内人になる端緒)。この成果によって弘安の役での活躍に結びついてい った(安達家御内人となることは守護所での勤務や所職の代官職を得るという経済性と結 びつく)。それが絵詞成立の重要な契機である。もし建治に海東郷地頭職を得ていて、それ が絵詞成立の最大の契機になったのなら、建治に絵詞が作成されてもよいということにな る。 サクセスストーリーは文永、建治、弘安と時間を追って完成している。 Q それならば弘安以後に所領を得たと書くべきではないか。 A それならば建治に海東郷を得たと書くべきではないか。弘安の役はそこで終わりになっ ているが、建治には前後する文章がある。 Q 戦意高揚がなにより重要だから、恩賞はかなり与えたのではないか。 A 陳情したからすぐに恩賞というのはふつうではありえないと考える。それは季長の手柄 の程度、恩賞までの時間のなさから不可能だったという意味である。文永の役での恩賞は どの程度制約されたものだったのか。まず合戦に参加した鎮西武士はいかほどの人数だっ たのだろう。時代が下った多々良浜合戦時の数字は『梅松論』は尊氏方については京都よ り供奉のもの三百余騎、少弐方五百余騎としている。『太平記』『梅松論』ともほぼ共通する。 ほぼ信頼できる数字かと思われる。菊池方(宮方)については六万余騎(従者をいれれば一 八万人)としていて、三万とする『太平記』よりも倍近く多い。これは多すぎる数字であ ろう。ちなみに関ヶ原合戦の兵力動員は西軍八万人、東軍七万五千人とされている。 京都から落ちて少数者になった尊氏方は千騎弱であった。従者がつくから三千人であろ う。 文永の役の攻める側は『高麗史節要』によれば、蒙古・漢軍は二万五千、高麗軍が八千、 水手らが六千七百人である。騎馬武者(騎馬兵)は一万というところであろう。 肥前御家人の数は瀬野精一郎『鎮西御家人の研究』によれば、古文書に登場するものだ けで、七四、御家人である可能性の強いものが五八とのことである。大友文書に建久六年、 肥前御家人が一番各五人・二八番交替で太宰府守護所を警備したとする史料がある。この 史料については信憑性をめぐって議論があるが、番役を務める御家人が一四〇人いた。九 州全体では一二六〇人の御家人がいたことになる。蒙古襲来時にも同様とすると、かれら は子弟縁者を動員して、戦場に駆けつけたであろう。仮に三〇〇〇騎、従者が六〇〇〇人 いたとし、兵員配置の関係で、決戦場にのぞみ得たものがそのうちの三分二とすれば、二 〇〇〇騎、四〇〇〇人か。 いくぶん少ない気もするが、いずれの数字を採ってみても、恩賞を得たものが一二〇人 だったというのは相当に狭い門である。恩賞を得たものが5なら、得られなかったものが 95であった。実際にはもっと少ない数字になりそうである。ほとんどのものは少々奮戦 したとしても恩賞にあずかることはできなかった。幕府・恩賞奉行は「討死・分捕」に限 定という大方針の下、厳密な検討を重ねてきたはずで、それを突如変更することは無用の 混乱以外引き起こさなかったと考える。不可能というのはそういう意味である。
追加
竹崎季長が九州から鎌倉に上った意図・「見参」の意味